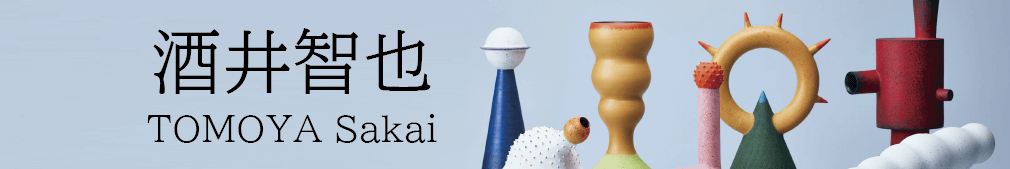酒井智也 陶作家・酒井智也インタビュー |「記憶」の痕跡を撫でる(前編)
作品は、どこか既視感のあるイメージである。
それらは人々の記憶に語りかけるように作用し、
思わずじっと見入ってしまうような、不思議な魅力を放っている。
今回の取材では、酒井のこれまでの制作を振り返りながら、彼の作品に迫る。
また、最新作、今後の展開についても聞いた。
編集・取材写真:B-OWND
PROFILE
酒井智也
1989年、愛知県生まれ。名古屋芸術大学陶芸専攻卒業、多治見市陶磁器意匠研究所修了。現在は、愛知県瀬戸市にて独立。主に電動ロクロを使って制作している。
主な受賞歴は、2020年、台湾国際陶磁ビエンナーレ 入選、2021年、第12回国際陶磁器展美濃 銀賞など多数。作品は、 京畿陶磁美術館(韓国)、新北市鶯歌陶磁博物館( 台湾)などに所蔵されている。
友人たちの死によって、将来を見つめなおす
-高校卒業後、大手自動車部品メーカーに就職された酒井さんですが、その後、美術大学に進学され、一時期は教員をされていました。その後アーティストへと転身されますが、これにはどういったきっかけがあったのでしょうか。
酒井 就職して2年くらいしたころ、大きな転機がありました。同世代の友人たちが相次いで亡くなったんです。その「喪失」に触れる度に、悲しさよりも「明日、自分も死ぬかもしれない」と強く感じるようになりました。そこから、後悔しない生き方について真剣に考えるようになったんです。
実は僕の両親祖父母は、みな教員なんです。小さい頃から仕事の話を家で聞くことが多く、やりがいのある仕事なんだと感じていました。自分の性格的にも教員に合っているかと思っていましたが、当時は大学進学よりも、はやく安定したい気持ちがあり、就職を選択しました。しかし、いざ仕事を始めてみると、新人の方々に機械の使い方などを教えることがとても楽しく、そこにやりがいを感じたんです。それを自覚してから、自然と教員を目指す気持ちになっていきました。
どの教科を専門にするかに関しては、美術一択でしたね。幼稚園の頃から絵画教室に通っていましたし、これからもモノづくりに携わりたいという思いがあったからです。そして、3年働いた会社を退職して、名古屋芸術大学へと進学しました。
-大学では、数ある専攻のなかでも「陶芸」を選択されました。
酒井 そうですね。ずっと絵を描いていたからこそ、自分の限界を感じるところがあったんです。一方で焼き物は、窯に入れたら自分が思った以上のものが出来上がるというイメージがありました。自分の手で作ったものに他の作用が加わることで、限界を超えられるような予感があったんです。
しかし、入学して1年目は、実際に土を触っても「楽しい」という気持ちにはなりませんでした(笑)。転機となったのは、大学2年生のころ、初めてロクロを触ったときですね。「あ、これはやばいな」と感じました。
―どういったところがよかったのでしょうか。
酒井 自動車部品工場で働いていたとき、旋盤を使った業務を担当していました。
旋盤というのは、金属の棒を機械に固定し、回転させながら削ることで部品を形成する機械です。当時から、回転体には惹かれるものがあり、出来上がった小さな部品から、SFチックな壮大なイメージを想像することがありました。実はそのときから、回転体に興味を持っていました。

写真:木村雄司
アーティストページ
作品販売ページ
でも、陶芸のロクロと工場で動く機械には、大きな違いがあります。機械には設計図があり、その通りにモノが出来上がりますから、そこに自分の感情は入る余地がありません。ですがロクロは、そのときの自分の感覚や、些細な感情の変化が、手を通じてダイレクトに表現できます。しかも短時間で、自分のイメージしたものが自分の手のなかで出来上がっていく。その感覚をすごく面白く感じました。
陶芸の制作は、常に刺激的です。特に窯焚きは、まるで神聖な儀式のように感じます。大げさに聞こえるかもしれませんが、それらの非日常的な制作行為が、自分が今、生きているという実感を与えてくれたんです。
ひとつの世界をつくり出す
写真提供:酒井智也
-大学時代には、そのロクロの技法で、青い釉薬のみずみずしい作品を制作されていましたね。
酒井 はい。この「青」の釉薬を使った作品は、「生命の誕生」というテーマでした。波紋をイメージしたグラデーションと、艶やかな釉薬が特徴の時代です。
「青」=地球や水、そこから生命が誕生するというイメージですね。それを、回転体であるロクロで作ることで、左右対称な世界、神聖さ、宇宙といったイメージなども連想していました。
写真提供:酒井智也
作品の見せ方も、器ひとつひとつの作品を見せるのではなく、インスタレーションとして見せることで、ひとつの世界を表現しました。作品を設置すると、その空間の雰囲気が変わりますよね。僕が当時表現したかったのは、例えば神社にいるときのような神聖なイメージなどが近いかもしれません。作品を制作することで、自分の世界をそこに出現させたいという思いがあるからです。
私が中高生の頃は、就職が今より難しい時代だったように思えます。まるで「現実を見ろよ」とでも言われているかのようで、理想を語ることがどこか難しかったんです。自分を取り巻く現状を変えるようなことは絶対にできないと感じていました。
今も社会を変えることはできませんが、自分の周りだけでも非日常的な空間を作り出し、そこに身を置いて浸りたい。そんな願望があるんだと思います。
ロクロで作り出した左右対称のシンプルなかたち、色、それらによって生まれる神聖な雰囲気は、自分の中で壮大なイメージを膨らませるのに適していました。それが、鑑賞する人にとっても、同じ世界に浸れるものであればいいなと考えていました。
写真提供:酒井智也
酒井 これは、卒業制作です。この少し前に、また身内の不幸があり、死というものをずっと考えていました。誕生もあれば死もあるけれど、それで本当に終わりなのだろうか。輪廻転生という言葉があるように、回転体で神秘的な宇宙や生命の流れを表現し、その流れのなかを、亡くなった人の魂を乗せた船が流れていくイメージで展示しました。
写真提供:酒井智也
当時は他にも、作品に光を当てて反射を見せるような作品など、器そのものだけではなく、空間を取り込むような意識で作品を制作していましたね。
―なるほど、酒井さんの現在の作品からも、設置した空間の雰囲気を変えるような作用を感じるのは、そういった視点で作品を制作されきたからかもしれません。
美術教師を経て、多治見市陶磁器意匠研究所へ
写真:木村雄司
アーティストページ
作品販売ページ
-その後、アーティストになるまでにどのような活動をされていらっしゃったんですか。
酒井 卒業後は予定通り教員になりましたが、制作に集中したいという思いが強くなり、結局2年ほどで退職しました。そして陶芸を専門的に学べる教育機関である「多治見市陶磁器意匠研究所」に入学し、ロクロでの表現を追求することにしたのです。
「多治見市陶磁器意匠研究所」の卒業制作では、ロクロ技術の限界にチャレンジするというテーマで、比較的大きな塔(タワー)を制作していました。回転体は、粘土と手の力の作用が層のように積み重なって出来上がるものです。そのときの環境や、自分の感情などに形が微妙に左右されながら、下から上へと層が重なっていきます。つまり、ロクロの縦軸回転に対し、横から手で力を加えることで徐々に出来上がる形です。人間も、さまざまな人との出会いや経験、自身の想いが積み重なったなかで人格を形成し、日々を生きています。そういった姿を反映した作品です。
また、これと同時期に、器の制作にも取り組んでいました。「青」以外の釉薬を用いて、カラフルな色彩を取り入れた作品の制作を始めたんです。
写真提供:酒井智也
写真提供:酒井智也
テーマは「新しい景色を生みだす」。シンプルな色・形の器を作ってテーブルの上で組み合わせるもので、言ってしまえばテーブルの上のインスタレーションという感覚でした。人々が生きる街中の風景の一角のような感じですね。展示で一堂に並べると、ひとつの街のようにも見えます。
―シュルレアリスムの絵画のような、どこか物語性を感じさせるような作品ですね。
酒井 このあたりが、現在の作品の母体になっていると思います。そこで気が付いたのは、結局この研究所時代も大学時代も、そしてもっといえば工場時代も、自分はさまざまな「形」を通して、記憶に残る情景を見ていたということです。小さな工場の部品から壮大なものを想像したり、器の波紋や映し出された陰影などもそうですね。そしてそれは、自分が見てきた映画、マンガやアニメなどの作品からきているのだと、自分のインスピレーションの源が、見えてきたのです。
そして新しい展開へ
-これらの作品作りを通じて、ご自身のなかで変化などあったのでしょうか
酒井 その頃、アーティストとして生計を立てていくことも意識するようになっていました。作家として活動を続けていくためにも「売れるものを作らないと」という気負いがあったように思います。
ですが、卒業後初のギャラリーでの展示では、作品が全く売れなかったんです(笑)。自分の認知度の低さなどにも課題があったと思いますが、それにしても思っていた以上に手ごたえのない結果に終わりました。
本音を言うと、器よりも立体的なオブジェが作りたかったんです。でも、生計を立てていくために売れそうな器を作っていました。そのはずなのに、売れないのなら器に向き合う意味ってなんだろうと。
写真提供:酒井智也
そうして至ったのは、工芸としての文脈を残しながらも、自身が作りたいものを作っていこうという、シンプルな答えでした。今まで作っていた細かな作品を組み合わせることで、新しい展開ができないか、という発想が浮かびました。
参考にしたのは、古墳時代の須恵器という焼き物です。須恵器は、日常的にさまざまな用途で使われるものでしたが、そのなかには、複数の器を組み合わせた種類があり、それらは儀式などに用いられたと言われています。僕の作品も、組み合わせることでワンランク上の器=「アート」にできるんじゃないか、という発想がありました。これが、現在の作品の始まりです。