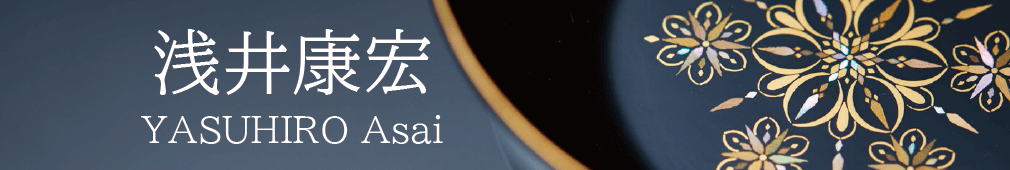浅井康宏 漆芸家 浅井康宏インタビュー|透明な思考、艶やかな記憶(前編)
浅井の作品には、掌の小品でさえ、
観る者に壮大さと深遠さを感じさせる。
ある時は慈雨のように、あるいは光の粒のように、
その表象を構成する要素の一つ一つが意識の上に降り注いでくる。
漆の美をまだ知らぬ人々へ、そして未来へ。
エバンジェリスト、浅井康宏の思考をたどる。
カバー写真:木村雄司
PROFILE
浅井康宏
1983年、鳥取県生まれ。2004年、国立富山大学高岡短期大学部 漆工芸コース卒。2005年、室瀬和美(重要無形文化財保持者)に師事。2011年、武蔵野美術大学 造形学部通信教育課程卒。2004年頃より、自ら漆の木を育て、現在はその漆を作品に用いている。受賞歴は、2002年、日本漆工協会 「漆工奨学賞」にはじまり、2012年、日本伝統工芸展 「新人賞」、2015年、第32回 日本伝統漆芸展 「文化庁長官賞」など、多数。
漆芸へ
―はじめに、工芸に進まれた経緯を教えてください。
浅井 鳥取県出身ですが、岡山の全寮制の高校に入ったんです。普通科の学校でしたが特徴的なところで、いくつものコースのなかに工芸コースがあり、漆を中心に教えていたんですね。そこで漆に出会いました。
そのときの先生が良かったんですね。おじいちゃんの先生で、君はもう開校以来の逸材じゃ、という感じで褒めてくれて。その学校自体、開校9年目ぐらいで、工芸コースはあまり人気がなくて 、年間1人とか2人しか入ってきていませんでした。だから、開校以来といってもせいぜい20人くらいなんですよね。その中で逸材って言われても、冷静に考えればクラスで一番、くらいのものなんですけどね。なんだかそれが嬉しくて。そこから漆にはまっていきました。
卒業後は富山県高岡市の短大に進みました。漆芸で進学するなら、ほかの選択肢もあったのですが、以前から明確に考えていたのが、早く作家になりたい、ということだったんですね。高校のときのその先生にもずっと、職人ではなく作家を目指せ、唯一無二のものをつくれ、ということを言われていまして、ふわっとしたカタチですが、作家というキーワードが、僕の頭のなかに早くからあったんです。それで、一番早いルートと思われた短大を選んだんです。技術を学んですぐに活動できるだろうと考えまして。早く自分でものをつくる方に行きたかったんです。

この作品で2012年第59回日本伝統工芸展にて新人賞を受賞
蒔絵螺鈿・杣田細工との出会い
―得意とされている技法に螺鈿を用いる杣田(そまた・そまだ)細工がありますが、この技法とはいつ出会ったのですか。
浅井 出会いは高校生の時なんです。京都の美術予備校に通っていた時期があるのですが、そのときに清水三年坂美術館で杣田細工の印籠などをずっと見ていたんです。なんかすごいものがある、と思っていましたが、当時はまだ、それが杣田細工というものだとは知りませんでした。
杣田細工はもともと富山の技術です。京都の職人だった杣田清輔(そまだせいすけ)が富山藩に抱えられて、富山で発展した地域性の高い技法なんですね。高岡の短大に進学してからそのことを知り、京都で見ていたあの技法は杣田細工だったんだと気づきました。
同時に、その作品を驚嘆の目で見ていた体験と、富山で発展した杣田細工の技法とが自分のなかでつながって、一気にそこに惹きつけられていきました。 高校時代に素晴らしい技法、作品に出会えてよかったなと本当に思います。
蒔絵螺鈿は高校時代から熱中していたものでした。蒔絵をやりたい、ということは早くから決めていました。そこから今日に至るまで、この決意はぶれていません。

写真:ふるみれい
漆の木を育てる
―鳥取のご実家で漆の木を育てていらっしゃるということですが、ご自身で育てようと思われたのはどういうことからですか。
浅井 漆から自分でつくりたい、という思いは以前からあったんです。祖父母が梨農家だったのですが、高齢になって木を伐採するとなったときに、ここに漆を植えようと、家族全員を半ばだまして(笑)植えたんですよ。それが17年前です。そこから育てて、やっと木が大きくなり、3、4年くらい前から漆を掻くことができるようになってきました。 漆は一度掻き切ってしまうと切り倒さなければなりません。でも、また横から次の幹が出てきます。そうやって繰り返し育てていくんです。漆の木はとてもかわいいですよ。

写真:星野裕也
浅井 その前から、漆を育てなければいけないという思いは漠然と持っていました。僕が漆を始めたときは、日本の漆の国内需要の98%が中国産だったんですね。2%しか国内産の漆がなかったんです。その頃までは、国内産の漆はとても冷遇されていました。中国産とそれほど違いがないのに、コストが数倍かかるんです。だから、国内で漆を掻いても買い手はつかないという状態でした。自分のなかに、このままでまずい、という危機感があったので、自分が使う漆は自分で育てるしかないと思っていましたね。漆の木を育て始めたのは、そういうタイミングだったんです。
でも、20年前と今とでは、見えている光景がまったく変わりました。平成30年から国内の文化財修復に使用する漆は国産でなければならないということになり、今ではむしろ、木も掻き子さんも足りないという状態になっています。なにしろ国産漆は高くて売れないものだと思われてきたので、後継者も育たず掻き子さんの高齢化も進んでいましたし、植林という機運も今ほどはなかったわけですから。こうした空白期間ののちに、漆を植えなければいけない、という流れが生まれ、現在は自治体が漆の木を植え始めたり、掻き子さんの研修が拡充してきた印象です。
漆づくり
―鳥取のご実家で育てている漆ですが、掻いたあとはどうされているんですか。
浅井 塗りの漆の場合はそのあとの加工を業者さんに頼んでいます。初漆といって、6月から採れる水分量の高い漆に関しては工房で加工しています。木クズなどがいっぱい入っていますので、自分たちでそれ漉してチューブ詰めにしています。
黒い漆に生成したりするときは、京都の漆屋さんにお任せして、京都の気候に合った漆をつくってもらっています。ベースに塗る漆と加飾に使う漆とはまったく違いますので、使い分けているんです。
これは、国産の漆、中国産の漆の違いにも共通することです。
漆の掻き採りは6月から始まるんですけど、6月の雨の多い時期の最初の漆は、初漆という水分量の多いものです。乾きの早い漆で、ちょっと透けが悪いので、摺り漆に使ったりします。夏の盛りに取れる漆は、透けがよく漆分の強い、塗りに使う漆です。産地や季節の特徴によって使い分けできるところが、日本産の漆の利点でもあります。

写真:星野裕也
浅井 一方で、大量に入ってくる中国産漆は品質が安定しているので、それに慣れれば扱いやすいものになります。
2017年の第1回の個展を終えたタイミングで、埼玉から京都に拠点を移しました。最初は漆が乾きにくくて、京都ではしばらく苦戦したんですね。
僕の実感ですが、冬の底冷え的な、夜ずっと同じ低い温度が続くとか、夏の夜ずっと同じ高い温度が続くといった京都の気候が、自分が持っていた漆にはあまり合わなかったのだと思います。
漆にも個性があります。それが育った場所の特性などから違いが生まれ、漆によって乾きやすい温度、湿度というものが違ってくるんですね。何千本もの木があれば、そこから集めた漆も標準的なものになりますけど、うちの場合は200本くらいの木を育てていて、年間20本くらいの木から採るので、どうしても木それぞれの個性とか、年による性質の違いというものが如実に現れてしまうんですね。そうなると、この湿度、この温度じゃないと乾かない、というものが出てきますので、その調整にちょっと時間がかかります。それで京都では最初の頃はかなり苦戦したんです。今は、機械的に高い湿度の環境をつくったりすることで、調整できるようになりました。
漆はそれぞれ個性があり、本当に「生きている」という感じがします。

写真:ふるみれい
今、京都に住んでいて、ずっとお世話になってきた漆屋さんに精製まで頼めるようになったのがとても嬉しいですね。今まで電話注文をして届けてもらっていたのを、今は実際取れたものを持って行って、精製されている過程を一緒に見ながら、こうやるんだな、と確認できるんですから。
漆に導かれて生きる

写真:ふるみれい
―漆だけでも、こうした繊細なたくさんの調整があるんですね。表現についてうかがいたいのですが、モチーフにされているデザインや、テーマについて教えてください。
浅井 そうですね、しいていえば、蝶が多いかなとは思います。でも、移り変わっています。実はモチーフやコンセプト面のこだわりはあまりないんですよね。ともかく漆が好きということだけなんです。漆をいかに見せるかが先で、それにふさわしいデザインを考える、という順番なんです。だから、確固たるテーマが実はないのが、自分ではちょっとややこしいなと思っています(笑)。
たとえば生き物を主題にした作家さんなどは、すごく生き物が好き、そして扱っている素材が好き、というベースが表現につながっていると思うんですけど、僕の場合、漆はものすごく好きだけど、ほかに何か、というものが特段ないんです。現代を生きている自分のフィルターを通して、いかに漆を美しく見せられるか、というところだけなんですよね。本当に漆という素材に引っ張られて生きているという感じです。
もちろん、漆という素材にはこだわる、そうしているうちに後からコンセプトがついてくるという感覚はあります。でも、コンセプトはちょっとこじつけみたいなところがあって、あとから考えて、こうだったんだな、という感じですよね。やはり手が先なんです。漆をいかに盛り上げていくか、という方向で手が先に動く感覚です。
結局、僕自身の存在より、漆なんです。漆という素材やその作品の方が自分より長生きすることがわかっていますから、僕よりすごい存在感だと思っているんですよね。そのすごい存在に身を任せていったときに、自分が思っていることと同期できるといいますか。
自分の人生よりも、自分がつくる作品・漆の存在の方が大きいという感覚は常にあります。たとえば正倉院の時代のものだったら、日本全体が仏教立国しようというムードのなかで、「今運んでいる作品は自分の命よりも重いのだ」という認識を持って運ばれてきたものだったと思います。そういうものを扱ってきた歴史というのが、僕の手のなかにも脈々とある。それと同じような気持ちでつくれば、それが1200年後にも伝わる可能性がある、という思いがあるんです。同時に、こうした歴史があるから、僕も今、漆でものがつくれるんだと思います。そういう意味で、1200年途切れさせなかった日本人の思いが、美意識の根底にあるんだと思います。
こう考えてくると、今自分が手にしている技は、借り物という感じがしてきます。あくまでも次に渡すためのもので、自分だけのものではないんですよね。自分の肉体を経由して次に受け継がれていくものなんです。

写真:木村雄司
【おしらせ】
7月2日(金)18:00より、浅井康宏氏の作品の販売がスタートします。
ぜひご覧ください。