奈良祐希 陶芸家・奈良祐希 インタビュー|境界を再定義し、新たな陶芸を切り開く変革者(前編)
陶芸家・建築家として活動する奈良祐希。
奈良が現在、創作創作のテーマとして掲げるのは、「建築と陶芸の融解」である。
そのひとつの答えとして生み出された代表作《Bone Flower》は、
いったいどのようにして生まれたのか。
今回のインタビューでは、
これまで他のメディアにも語られてこなかった本作の誕生までの道のりを辿ることで、
奈良祐希という鬼才のアーティストに迫る。
作品写真:Shugo Hayashi
その他写真:波多野功樹
PROFILE
はじめに 《Bone Flower》とは―作品名に込められた意味
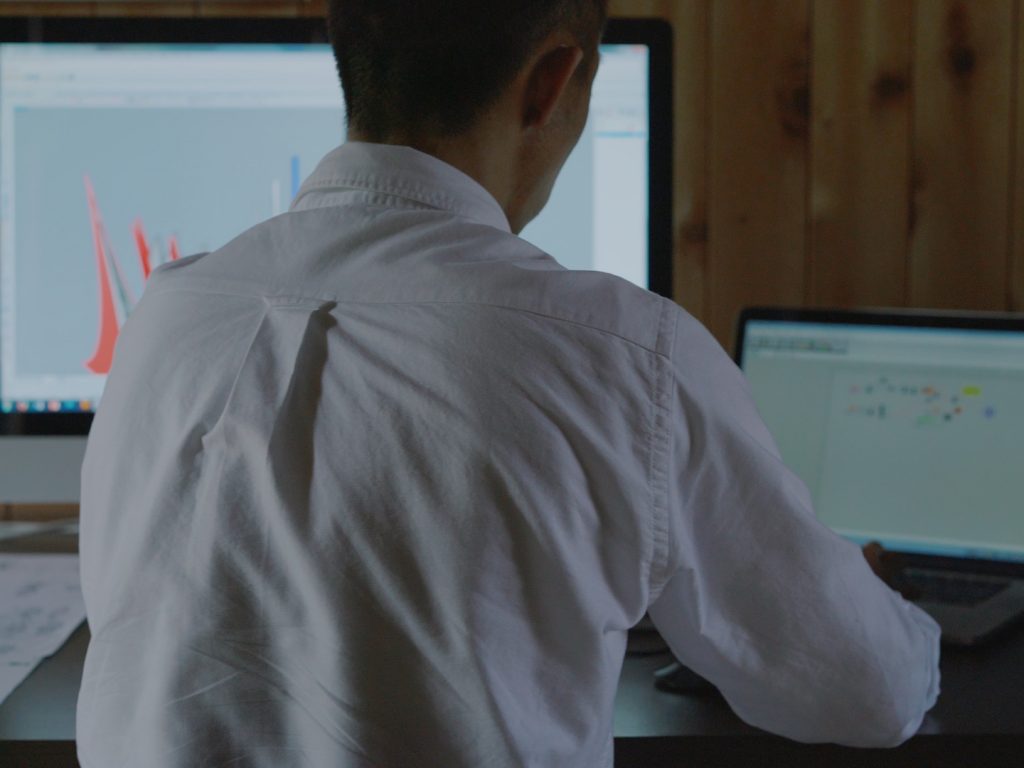
――《Bone Flower》は、作品名がとてもユニークですが、どんな意味が込められているのでしょうか。
奈良 きっかけになったのは、祖父(※1)が僕の作品を初めて見た時に「骨の花みたいだ」と言ったことからなんです。よくよく考えてみると、この作品をダイレクトに表現している言葉だなと思いました。
僕の作品は、まず頭の中にあるイメージを現実化するために、膨大な量のスケッチを描きます。それから3D CADやプログラミングといった最先端のテクノロジーを使用しながら、スケッチの断片をリアルな形として設計していきます。ここまでは“建築”的なフェーズで、次から、“陶芸”的なフェーズに移行します。長い時間をかけて土の板をひとつひとつ制作し、それを切削しながら組み合わせ、最終的には1280℃以上の高温で焼成するという手法をとっているのですが、そこにもこの骨と花という、キーワードに意味を見出せるんです。
たとえば人間は、生まれたときにはある形が定まっていて、骨は成長とともに大きくなっていく。同じように、3D CADを使って作品を設計する段階でも、決められた形の中で構成していきます。でも花っていうのは、光合成や育つ場所といった様々な自然環境のコンディションに影響されて育つ。もともと遺伝子という設計図はあるんだけど、必ずしも純粋にその通りの形にはならない。陶芸も、土が生き物のように環境によって変化していくから、必ずしも設計図通りにはならないですよね。だから骨と花ってすごい対比されている表現だと思うんです。そしてその対比が《Bone Flower》にも重なる。だから見た目はもちろん「骨の花」なんですけれど、作品の本質も捉えたメタファーでもあります。
建築を学び、そして“土”にも触れた大学時代

――奈良さんは、350年以上続く茶陶の名門、大樋焼(※2)のご長男としてお生まれになり、おじい様、お父さまも陶芸家でありながら、ご自身は20歳を過ぎるまで、陶芸は一切やらなかったそうですね。むしろ、ものを作るということ自体をやりたくないと。この流れの中でなぜ建築科に進まれたのでしょうか。
奈良 理由は2つくらいあるのですが、ひとつは、僕の地元にある金沢21世紀美術館の存在がありました。そのあたりが僕の高校の通学路で、建ち始めから完成までを毎日ずっと見ていた。この美術館は、金沢にとってとても意味のある建築で、これによって街が変わったり、人がたくさん来たり。そういう変化を直接肌で感じて、建築に大きな可能性を感じていました。あとは父(※3)の勧めですね。建築って、人間が創造するものの中で一番大きな芸術だから、大は小を兼ねるじゃないけれど、そういう大きなものを学んで、収束していくっていう捉え方があると。当時高校3年生のときはピンっとこなかったんですが、今はなんとなくわかる気がしています。建築を学んでいた人で、ほかにも活動の幅を広げている人たちって、けっこうたくさんいるじゃないですか。僕が陶芸に興味を持つかどうかはさておき、大きなものを学んでから、あとは自分を考えろよ、っていうことだったのかもしれないですね。
――そして在学中、あれだけ遠ざかっていた陶芸も始められましたが、どんなきっかけがありましたか。
奈良 実は大学生の頃、遊びすぎちゃって、留年したんですよ(笑)。その時って、3年生から4年生に上がるタイミングで、これからの自分の進路についてとても悩んでいた時期でした。卒業してそのまま建築事務所に入るか、大学院に進学するか。それとも海外に留学するか。建築って面白いなって思っていたけれど、自分が将来建築家になるかどうか、ってちょっとまだわかっていなかった。けれど、今までずっと嫌だと思っていた「ものを作る」ことに、大きな喜びを感じはじめていました。
そんなときに留年したんですが、もう金曜日の朝の9時の授業だけ出ていればよかったから、本当に時間が有り余っていました。そのとき父が「じゃあ、金曜日以外は金沢にいたら?」って。
遊びすぎてしまったこともあるし、人生もう一度悔い改めろよって、そういう戒めのメッセージも込めての進言だったと思います。そこで、初めて実家の工房を見てみようかなという気持ちになりました。しばらく通い続ける中で、陶芸の勉強をしてみたくなりました。実家の工房でもいいんだけど、ある程度は緊張感を持って取り組むために、知り合いの方の陶芸教室へ通い始めるんです。ロクロとか、土の揉み方とか陶芸の基礎的なことから習い始めたら、意外なほど楽しくって。
大学の課題では、建築って、実際に建てることなんてほとんどないから、設計して小さな模型を作って終わることが多いのですけど、陶芸って自分で考えたものがそのままリアルに自分の手で作れてしまう、1:1の世界でした。そこにすごく魅力を感じました。
――この頃はどんな作品を作っていましたか。

奈良 基礎的な技術の習得を目指していたので、課題に取り組む日々でした。同じ大きさの器を100個作ったり(笑)。しばらくして、先生から自分の考えた作品を作って良いという許可が出て、最終的に出来上がったのが、ブロックを積み上げたオブジェみたいなものでした。それが、本当の先駆けになるのかもしれないんですけど、建築のように、図面をハンドドローイングでちょっと書いて、その設計図通りに土で制作してみるということをやったんです。でも当時は、本当に土のことを知らなかったから、乾燥してヒビが入ったり剥離したりとか、焼いて割れたり、結局設計図通りにならなかった。そういうのはあったんですけど、やっぱり建築と陶芸を等価に考えてみようというスタンスはあったんだと思います。
「建築と陶芸の融合」という命題
――建築の考え方を陶芸にも応用されたのですね。奈良さんは、この陶芸教室での経験を端として陶芸を続けていくことになりますが、建築との両立は初めから考えていたのでしょうか。
奈良 4年に進級して、卒業制作に取り組んだのですが、実はあまり納得いくものができなかった。結局そのまま大学院に進学するのですが、自分の目指す建築がわからなくなっていったんです。考えてみれば大学院は2年間であっという間に終わってしまう。このままでは絶対に何も掴めないまま修了するなと思って。
そこで、一度本格的に陶芸を勉強して自分のルーツを知ることで、改めて建築に取り組むのも、ひとつの道かなと思ったんですよ。それから大学院を休学して岐阜県にある、多治見市陶磁器意匠研究所という専門学校に2年間通うことにしたんです。「建築と陶芸の融合」を命題として、そのゴールのために2年間全力で頑張ると。実は《Bone Flower》の起源は、その学校の卒業制作なんですよ。
――《Bone Flower》ができるまでには、どんな試行錯誤があったのでしょうか。

奈良 意匠研究所の卒業制作に取り組む前の最後の課題になるのですが、「日本的なるもの」というものが出ました。そこで初めて、日本の精神性や文化性から改めて陶芸を捉え直してみようと思ったんです。様々なところからヒントを得ました。伝統的な日本建築の様式、寺社仏閣の構造や小さなエレメントの集積などです。実家が武家屋敷なので、幼少期から日常的にそういったものを見ていたことで原風景としてリアルにイメージができました。
――奈良さんの作品からは、磁器でありながら固すぎず、生き物のような、なにか有機的なものも感じます。

写真:Shugo Hayashi
奈良 やっぱり土って、生き物の感じがあるじゃないですか。乾燥の段階でじわじわ変わってくるし、焼いて全然乾燥の状態とは違ったかたちとして現れてくるときもある。そういう有機的な要素が作品に入ってほしいと、ずっと思っていたんですけれど、ヒントがないなあと。層で重ねただけだと、すごく機械的だから、もう少しそこに生命を感じるような「土らしさ」が欲しいなって思っていて、どうしたら表現できるか、ずっと考えていた。そんな時に、ちょうど目に留まった風景があったんです。
僕は、結構走りながらものを考えたりするのが好きで、多治見にいたときは、毎朝走ってたんですよ。いつも河川敷がそのルートだったんですが…、ある日、イネ科の植物だと思うんだけど、それが風で波のようにザァァァッと様々な方向になびいていた。もう、全然理由はわからないんだけど、そのごく普通の風景に目が留まって、気が付いたらその風景をずいぶん長い時間、立ち止まって見ていました。それ、今でもはっきりと覚えているんですけど、かなりの密度で自生していたんです。下はもう隙間もなくぎっしり。でも上のほうはこう、すぼまっていているから隙間もあって、風でなびいて揺れたり、揺れなかったりする。バラバラに群生する植物がひとつの生命体のように感じて、これめちゃくちゃ面白いなぁって思ったんです。
――作品に、植物の群生する様子や、それらが風になびいている様子が感じられます。奈良さんは「境界」をテーマに制作をされていますが、日本建築における「境界」からは、どのような発想を得たのでしょうか?

奈良 器や従来の荘重なオブジェは、裏と表がどうしても出来てしまいます。そういう境界のない、ある種の曖昧さをもった作品を作ろうとしたら、どんなものができるだろうという考えはありました。日本建築は、外と内をゆるやかに繋げる襖や蔀戸、障子などの様々な境界のフィルターが存在する。外と内は限りなく等価で境界は軽く、儚いんですよ。日本建築のように周辺の環境を引き込みながら、絶えずその場所固有の空気を内包するもの。障子が光を、柔らく取り込むように、外と内とを優しくつなげていく、暖かな境界をもった陶芸を作りたいとずっと考えていました。
僕、小さい頃から創意工夫、創育工夫っていう言葉を言われ続けてきたんです。それは祖父の言葉なのですが、自分しか作れないものが何かをずっと考えろって、彼は僕に言い続けていた。その言葉がずっと、現在でも脳内でリフレインしているんですけれど、僕は創意工夫って、言い換えれば何かを疑い続けることではないだろうかと思ったんです。実際に疑わないと創意工夫ってものは生まれない。自分にしか作れないものをどう生み出すか、ずっと頭を悩ませていましたけれど、僕の場合は、一番のヒントになったのが、建築と陶芸を等価に考えることだったんですね。
「境界」は誰かが都合よく決めた領域分けに過ぎません。 1本の線で分けることをやめてみると、それらの間には、無限の色彩や階調のグラデーションが広がっていることに気が付きます。既成の概念を超えて、自分にしかできないものはなにかと、深く突き詰めていったことで、現在の「境界」というテーマにたどり着きました。
WORDS
※1 祖父
大樋陶治斎(十代 大樋長左衛門)。1927年、大樋窯九代長左衛門の長男として生まれる。東京美術学校工芸科卒業(現・東京藝術大学)。2011年、文化勲章受章、2016年、大樋陶治斎を襲名。茶陶を手掛けてきた大樋焼の伝統を受け継ぎつつも、歴代で初めてオブジェなどを制作し、大樋焼の幅を広げた。作品は、宮内庁、東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、金沢21世紀美術館などの国内はもちろんのこと、メトロポリタンミュージアムをはじめとする、アメリカ、フランス、ベルギーなどのミュージアムにコレクションされている。
※2 大樋焼
大樋焼は、江戸時代前期より京都の楽家の脇窯として、350年以上続く茶陶の名門。 主にロクロなどを用いない手作業で作られており、温かみのある形や、飴色の釉薬が特徴的である。大樋焼は陶器の中でも軟陶と呼ばれ、口当たりが柔らかく、保温力にも優れている。 1990年、初代から現代に至るまでの大樋焼作品と、加賀藩に縁が深い茶道具などを展示する「大樋美術館」がオープンした。また2014年には、隈研吾氏設計によるギャラリーも新設された。
※3 父
十一代 大樋長左衛門(陶芸家・デザイナー)。1958年、十代 大樋長左衛門(現・陶治斎)の長男として生まれる。1984年、ボストン大学大学院修士課程修了(M.F.A.)。陶芸家として精力的に活動する傍ら、陶壁の制作、設計監修、空間プロデュースを手掛けるなど、幅広く活躍。ほか国内外の大学の客員教授として、後進の指導にもあたる。近年の受賞歴は、2018年、第57回日本現代工芸美術展「文部科学大臣賞」、2019年、改組新第6回日展「東京都知事賞」など多数。作品は、日本国内のほか、ヨーロッパ、アジア、アメリカ、ブラジルなど世界中のミュージアムに所蔵されている。