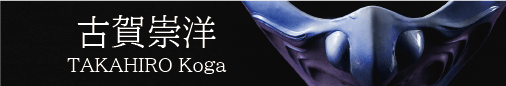コレクターズインタビュー デザイナー・アートディレクターが語る|作品とともに過ごす「ひととき」が与えてくれるもの
デザイナー・アートディレクターとして活躍する平大路拓也さんにお話を伺います。
「作品は、心を解放してくれるもの」と語る彼に、
アート作品に興味を持ったきっかけや、お気に入りの作品についてお話いただきます。
写真提供:平大路拓也
PROFILE
平大路拓也
Designer | Art Director.
1985年、東京都生まれ。
東京工芸大学芸術学部を卒業。2014年に独立。
事業アイデア、コンセプトメイキングをはじめ、グラフィック、ウェブ、モバイルアプリなどトータルでデザイン・アートディレクションを行う。
代表的な仕事に、バッテリーシェアリングサービスの「ChargeSPOT」、入浴剤の「BARTH」など。クライアントと伴走しながら創造する仕事とともに、最近は地方や公園などを盛り上げる仕事も行う。アイスハンバーグ株式会社 代表取締役。
モノを見て、考える視点を育んでくれた父の存在
―まずは、平大路さんのお仕事についてお聞かせください。
平大路 デザインやアートディレクションによって、様々な課題を解決する仕事をしています。たとえばそれは、企業や地域のロゴやウェブサイトをデザインすることであったり、ときにはブランドそのものを一緒に作り上げて長期的に伴走していくこともありますので、コンサルタントにも似通っている部分があるかもしれません。
僕の仕事は、単に言われたものを作るのではなく、なぜこのブランドや精神を世の中に出していくのかという背景の部分まで理解したうえで、物事を解決するデザインを提案することです。クライアントと、ひとつのプロダクトを磨き上げていくような方針で仕事をしています。
―「背景の部分まで理解する」という姿勢でお仕事をされていらっしゃるんですね。

平大路 はい。それには、1つ1つのプロダクトがどうやって出来上がったのかについて、子供時代に父とよく話していたことが関係していると思います。
僕の父は、本当に多趣味な人で、カメラ、オーディオ、車、時計、そして日本刀まで、幅広い領域を深くまで知り尽くしていました。自宅にさまざまな希少な車があったり、博物館で飾られるようなカメラで家族の写真を撮ってくれたりと、とにかく一流に触れさせるという教育方針だったようです。テレビの上には700年前の日本刀や刀剣辞典の表紙を飾っていた槍が置かれていて、小学生の僕に詳しく話してくれました。今思うと、子ども相手に700年前の日本刀について語るのは、いろんな意味ですごいなと思います(笑)。
ですが、プロダクトが生まれた背景や歴史、そのモノの美しさなどを父が詳しく話してくれたおかげで、モノを見て考える視点が育まれ、現在の仕事や趣味などに繋がっていると感じています。
他者の作品に初めて目を向けるきっかけとなった体験
―幼いころから世界の優れたプロダクトに触れてきた平大路さんですが、現在はアート作品を自身で購入されていらっしゃいます。プロダクトではなく、アートに興味を持ったきっかけなどはあったのでしょうか。
平大路 僕は大学生時代にグラフィックデザインを専攻していたのですが、一時期、たくさんのものに触れれば触れるほど、自分の表現がわからなくなってしまったことがありました。
悩んだ結果、自分の好きなことをそのまま表現してみようと、大好きだった工業製品を使った巨大なインスタレーション作品を制作しました。そのときは、とてもやり切った感がありましたね。自分が大好きなものを表現することの気持ち良さを初めて知りました。そして、作品は自分の分身であると感じ、同じようにいろんな作家がいろんな分身を作っているのだと思いました。「この世の中には、どんな作家がいるんだろう?」と、それまで以上に他人が作る作品への興味が湧いてきました。
―デザイナー、アートディレクターとしてクリエイティブな仕事をされている平大路さんですが、ご自身がアート作品に求めるものはなんでしょうか?
平大路 今僕は、デザインの領域に関わる仕事をしていますが、やはりデザインとアートは違うものなんですよね。アートは妥協がなく、自分のエネルギーの塊のようなものを生み出すことだと思います。そこには余分なフィルターもなく、まっすぐです。
しかしデザインは、誰かに応えるものでなくてはいけません。そこに様々な人たちがいればいるほど、本来持っていた一番伝えたかったことが薄れていくようなことが往々にしてあります。そういうときに身近にアートがあると、そこに溢れるエネルギーに気付かされ、心が動かされる瞬間があるんです。
人の精神状態は、常に何かに触れて変化し続けていくものなので、いかに環境をエネルギーあふれる状態にできるか、それが僕にとって非常に重要だなと思っています。
お気に入りコレクションの魅力

作品ページはこちら
アーティストページはこちら
平大路 これは陶芸家・市川透さんの茶碗で、はじめて市川さんの作品を拝見したときに購入したものです。展示されていたすべての作品からは、現在の市川さんを作り上げたであろう、人生の壮絶な体験がにじみ出ているように感じ、僕にとっても衝撃的な体験でした。
この作品は、そんな市川さんの作品のなかでも、少し毛色の違う作品といえるかもしれませんね。色合いも穏やかで美しく、「厳しいなかにある優しさ」のようなものを感じて、一目ぼれで購入しました。アート作品を初めて購入したのがこの作品で、その点もとても印象に残っています。

作品ページはこちら
アーティストページはこちら
平大路 陶芸家の古賀崇洋さんの盃です。造形美にとても惹かれた作品です。車などもそうですが、面の取り方がすごく綺麗だと感じました。横から見たとき、真上から見たときそれぞれに異なった表情が表れるのがいいですね。
また、古賀さんご自身が掲げる「下剋上時代の陶芸」というコンセプトにも共感しています。生まれがどうこうではなく、現代は誰もがチャンスをつかめるフィールドに立っているという考えには納得感がありますし、黙っていたらもったいないなと思わせてくれます。保守的に生きるのではなくて、前のめりに取りに行く姿勢で生きなくてはと、いい刺激をくれる作品です。

写真提供:平大路拓也
平大路 写真家の佐藤さんは、実は大学時代からの友達です。大学卒業とともにニューヨークに移住し、写真家として挑戦していました。ちょうど昨年、日本で展示をする機会があり、久しぶりにいろいろな話を聞きながらじっくり作品を拝見しました。その展示で購入した作品がこちらです。
彼は、今も昔もずっとストリートのなかに身を置いて、ニューヨークのストリートを撮り続けています。その被写体は、ダンサー、メッセンジャー、スケーターからプロのスポーツ選手まで多岐にわたりますが、ストリートで生き続けているから切り取れる感覚が、とてもかっこいいと思います。
この作品は、電車の車内に日が差した様子を撮ったものです。ずっとストリートに身を置いていた彼だからこそ、瞬間的な光の美しさを切り取れたんじゃないかなと思っています。
電車ってニューヨークではごく一般人の乗り物というか…裕福層はタクシーとか自家用車を利用するでしょうから、そういう意味でも電車に「光」が差すというのが、いいなと感じたのです。この「光」は、彼らの何気ない生活のなかの希望にも感じられますし、または彼ら一人ひとりが英雄的にたたえられているようにも感じます。解釈の仕方は色々あると思うのですが、貧しくて厳しいなかにも希望はあるし、そこにいる人たちの生き様に対する共感とか、そういう眼差しを感じて、とても気に入っています。
アートは、日々を豊かに生きるために

―平大路さんにとって、作品を「見に行く」のではなく、「所有する」醍醐味はなんでしょうか?
平大路 なんでもデジタル化が進んでいる現代では、直接五感を使って物事に触れるという機会がかなり減っていると思います。情報が溢れかえっていますし、画面上で見ただけで理解していると思っている人が多いのではないでしょうか。ですが、実際は触れてみないとわからないことがたくさんあり、直接触れたときの感動を超えるものはありません。
誰でも、美術館に行って作品に触れて気持ちが動く瞬間があると思います。でもあれって、三日ぐらい経つと感動が薄れていく。だから、その気持ちをまた起こせるようなもの=アート作品を身近に置くことは、人生をとても豊かにしてくれることだと思います。
多くの人がさまざまなストレスを抱える現代ですが、それを解放させてくれるスイッチみたいなものが作品にあるとすると、アート作品を身近に置くことは大きく生活を変えてくれるものだなという感じはしてますね。
―最後に、平大路さんにとって、アート作品とはどんなものでしょうか。

平大路 「心を解放してくれるもの」かもしれないですね。誰かがいろんなエネルギーを込めて作った作品は、それと向き合って鑑賞するなかで「なんでこういうものを作ったのだろう、どうしてこういう表現にしたのだろう」と、忘れていた自分の何かに触れさせてくれる機会になります。たとえ親しい人に悩みを打ち明けている時間でさえ、多少のノイズが入るものですが、作品と過ごす親密な時間にはそれがなく、とても貴重な時だと思います。
人には、生活のさまざまなシーンにおいて、そのときにしか動かせない感情や頭の部分があるような気がしています。たとえば恋愛であれば、大切な人と別れてしまって会いたいけれど会えないという思いは、仕事にも趣味にも代えられない、そのときにしか味わえない感情です。 作品に関して思いを馳せるひとときも、他には代えられないですね。このかけがえのない時間が、アート作品が自分にもたらしてくれるものだと思います。
関連記事