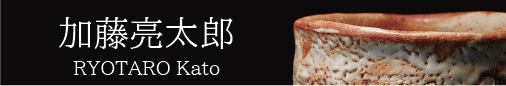家でアートを楽しむオンラインイベント「Stay at Home with ART」 「Stay at Home with ART」企画第1弾 陶芸家・加藤亮太郎氏とオンライン飲み会を開催しました
「Stay at Home with ART」企画第1弾である陶芸家・加藤亮太郎さんとのオンラインイベントを開催しました。このイベントは、対象作品を購入いただいた方と陶芸家・加藤亮太郎さんが購入したぐい呑を片手にオンラインで飲み会をするというイベントです。お話は、作品の解説から酒器にあった日本酒や、土の話まで広がりました。そんな大変、盛り上がったオンラインイベントの様子を加藤さんの作品のお話を中心にご報告します。
PROFILE
加藤亮太郎 1974年、200年以上続く幸兵衛窯の7代目・加藤幸兵衛の長男として生まれる。1999年京都市立芸術大学大学院陶磁器専攻修了。2000年より幸兵衛窯に入る。2015年幸兵衛窯8代目を継承。伝統的な美濃の焼き物からオブジェまで、幅広い作風を展開する陶芸家。
「オンラインでも、みなさんとお酒を酌み交わす機会をいただけて嬉しいです。」と陶芸家・加藤亮太郎さんの挨拶から、本イベントは始まりました。
外出ができない今だからこそ、住んでいる場所にかかわらず、みなさんで顔を合わせて語りあえるオンライン飲み会を開催しました。
オンライン飲み会とは、ZOOMなどビデオ通話ができるオンラインツールを使って、インターネットで繋がった人たちと一緒にお酒を飲みながら、会話を楽しむことです。
本イベントでは、加藤亮太郎さんが作品をつくる様子の写真などを用いながら、作陶や作品について解説してくださりました。この記事では、その一部を紹介していきます。
加藤亮太郎さんの作品について
――まずは、作品の解説をお願いします。
<志野焼>
「志野は、日本で最初に生まれた白い焼き物といわれています。」

「志野焼は、(加藤亮太郎さんの)祖父(6代目)加藤卓男氏が50年ほど前に作った桃山時代の様式の半地上式穴窯で焼成します。
その前は曽祖父が作った登窯という部屋がいくつも重なる窯で焼成していましたが、それを壊して、穴窯を築き直したんです。穴窯は、祖父の代から私(8代目)まで代々使っています。 その窯で5日間かけて焼成し、1週間冷まして窯出しをしています。」

「5日間ずっと窯に薪をくべ続けるので、赤松の薪をトラック2杯半使います。
そうすることで、白い釉薬がじわじわと溶けて、「ゆず肌」と呼ばれるピンホールがいくつもある、みかんの皮のような、もちもちとした表情が出るようになります。
1週間かけて冷ますことによって、釉薬が薄い部分にオレンジ色に似た「緋色」と呼ばれる色が出る。小説家の川端康成が「千羽鶴」という小説のなかで、志野焼を『日本人女性のもちもちとした白い肌、紅を差したような緋色』と表現しています。このように、日本人が親しんできた技法として「志野」があるんです。
元々は中国の染付や白磁を真似て作られたのですが、結果的に全く違うものになって、「志野」が生まれました。
これも織部と同じように歪んだ形をしていますが、本来は織部の範疇として生まれたものです。その派生として、「茜志野」や「鼠志野」などが生まれてきた。それらは、釉薬の調合の違いに由来しています。」
――加藤さんは5~6種類くらいの「志野」を制作されていますが、同じ穴窯で同時に作っているのですか?
「はい、同時に作っています。もともと、ガス窯や電気も使っていましたが、穴窯で焼くと釉薬や土の質感が出て味わい深くなるので、今はすべて穴窯で焼いているんです。「紅志野」は、白い釉薬の中に鉄を入れることで赤みを出しています。」

<黄瀬戸>
「黄瀬戸には、木灰を使っています。桃山時代にできた焼き物です。灰釉薬には、微量の鉄分が入っているため、黄色くなります。
そのなかには、鉄で茶色が出ていたり、緑色の胆礬(タンパン)という銅の発色が出たりして、さまざまな色が混ざっているものもあります。 中国では青磁を作るために、空気をあまり入れない還元焼成を使っています。これに対して、酸化焼成という酸素をたくさん入れる焼成方法があります。この場合は、仕上がりは黄色くなるんです。それが、この「黄瀬戸」です。美濃焼のなかでも通好みの技法といわれています。」
――この飲み口の曲線は予め形を決めているのでしょうか?
「形はろくろの回転と自分のバイオリズムを合わせてできるものなので、自然な造形なんです。
形ができたら、釉薬をかけて景色を作って仕上げています。 釉薬の色合いをどう出すかは考えていますが、全部が思ったようにいくわけではありません」


<椿手>
「灰釉の中に微量の鉄を入れると、黄瀬戸のように黄色くなります。
鉄の量が増えると、黄色→オレンジ→赤→茶色→黒の順で色が変化します。
鉄の量と、焼成時の酸素の量を調整することでいろいろな色が出るので、それを駆使して作ります。
鉄の量と、焼成時の酸素の量を調整すると、さまざまな色が出るので、それらを活かして作っていきます。 そのなかで、赤い色が出ることがあって、それが椿の花に見えることから、「椿手」と呼ぶんです。 椿手には黄色や赤も混在しているので、多種多様な姿を見せる作品といえます」

<織部>
「織部は、緑を発色する銅が入った釉薬を掛けて焼成しています」

「この穴窯で焼成しています。先ほどの窯よりも、ひと回り小さい窯で引出し黒という瀬戸黒を焼くために作られた窯なんです。この窯の奥に織部を入れて焼いています。
織部には引出しという技術は用いません。ただ、窯の中で、赤松の薪の灰が飛んでかかり、ターコイズブルーの色が出ることがあります。穴窯ならではの変化が楽しめるものですね。 (茶碗を手にして)口もとが灰の影響で焦げて黒くなっていますね。これは、窯の中の置く位置によって灰の掛かり方が違うことで生まれる変化です。そのため、窯詰めも大切なんです」
「織部は歪んだ左右非対称な形をしています。 千利休の桃山時代にあとを継いだ古田織部の好みで左右非対称になったといわれています。
ただ、あえて曲げているのではなく、使いやすさ、持ちやすさを配慮した形なのではないかと思っています。茶碗は、右手で持ち、左手を添えて持ちますよね。つまり、左右非対称で持つことになるんです。
両手で左右非対称に持てるように、くびれを作ったり、手に収まるように歪ませて作ったりしたのが織部なんじゃないか。だから、非常に持ちやすく、使いやすい形になっているのだと思うんです」
――加藤さんの作品に使用している土は全部同じものなのでしょうか。
「はい。もぐさ土という種類のものを使っています。ただ、作品によって、土の状態が違います。例えば、志野と瀬戸黒には、ざっくりとした白い土を使っています。黄瀬戸や椿手は、鉄分が多いものを用いています。織部の場合は、焼き上がりが引き締まる効能を持つ土を選んでいます。すべて美濃の土ですね。」
――土は自分で取ってくるのでしょうか。
「基本的には自分で取ってきています。もちろん、買うこともあります。幸兵衛窯は、食器のメーカーでもあるので、たくさんの土屋さんと取引があります。食器メーカーとして焼く食器には、精製されている土を使っていますね。
私の作品には、自然の土を使うようにしています。父(7代目)が掘ってきた土、自分で掘った土、あるいは土屋さんが用意した掘りたての土を使っています。木の根っこや石が混じっている原土を乾かして、叩いて、ふるう。そして、水で溶いて、泥にして乾燥させてから、土を練って使っています。これは、原始的なやり方です」
陶器と日本酒のマリアージュ
――陶器とお酒とのマリアージュはどういった視点で選んでいるのですか?
(今回、B-OWNDのFacebook(投稿はこちら)の日本酒を選定してくれた方が答えてくれました。)
「今回は、私が手に取る前に日本酒を選んだので、作品のイメージ、地域、そして一般的な陶器と日本酒の相性から選定しました。
一般的には、陶器にはぬくもりを感じさせるイメージがあるので、温かみのある日本酒が合うといわれています。
また、ガラスや磁器は冷酒など清涼感のあるものと相性が良いといわれています。
あとは、窯のある地域の地酒とそこで生まれた伝統工芸を合わせれば、その地域の文化や歴史に気持ちを乗せて飲めるので、より楽しめるのではないかと思って選びました」
――加藤さんも、ぐい呑によってお酒の味は変わるとお話されていました。
「人間の唇の感触は繊細なので、口当たりで味わいは変わるんですよね。味というのは器の素材や形状の違いなどで変わります。だから、酒器とお酒の組み合わせは、複数あるといってよいでしょう。
志野でいうと口元が分厚く、つるんとした釉薬なので、口当たりがまろやかになり甘みが増すのではないかと思っています。
例えば、「志野」は口元が分厚く、つるんとした釉薬を使っています。だから、口当たりがまろやかになって甘みが増すのではないかと思っています。 逆に、磁器のようなものだと、口元が薄いので辛く感じるのではないかなと。あと、開いた形だと香りがたつので、熱燗向きです。閉じた形だと香りがこもる、など、器とお酒の相性も楽しめるんです」
穴窯はどのくらいもつのか?
――穴窯はどのようにメンテナンスされるのでしょうか。
「穴窯は、おおよそ50年経っているのでボロボロですが、よほど崩れたりしない限り、補修はしません。穴窯は、表面にとても細かいヒビがいくつも入っています。その隙間から炎が吹き出すことがあります。それによって、ヒビから空気が入り、作品の表情に影響するので埋められないんです。もし、ヒビを完璧に埋めてしまうと、仕上がりは変わってしまいます」
――焼いたときの赤松の灰は、焼くたびに出しているのでしょうか。
「赤松の灰は8~9割は煙突から飛んでいってしまうんです。
灰の一部は炉壁について、ドロドロに熔けちゃいます。なかには、手前から掻き出すこともあります。焼成の後に残ったものは、釉薬の原料にすることもありますね。」
――窯はどのくらいもつものですか。
「屋根があって、雨風などに当たらないのであれば、長期間にわたって使用できます。今、使っている穴窯は50年前に作ったものなんです。ただ、雨風などが当たると劣化することもあるので、もたないこともあります。」
自分らしさと火の神に託す想い
――加藤さんは8代目ですが、後継者になるというプレッシャーのなかで、陶芸の道に進むと決断したタイミングは?
「徐々にですね。大学受験を考えたときに、美術系の塾に通い出したんです。ストレートに陶芸をやりたいというよりも、絵画や現代美術のほうに行きたいと思っていたんです。しかし、陶芸科しか受かりませんでした(笑)。陶芸科に進みましたが、現代美術がやりたかったので、オブジェばかり作っていましたね。
卒業後、実家の幸兵衛窯に戻ってきてから徐々に器を作り始めました。ずっと見てきた祖父や父のようにはなれないので、自分なりの特性・長所を作家と結びつけていくしかない。お茶や書道も好きだったので、それらを活かすことにしました。今となっては、自分らしさになっていると思っています」
――作品を窯に入れるときはどのような気持ちなんでしょうか?
「窯に作品を入れるときは、自分の思いを込めますね。作品の完成を最後に火の神様に託し、祈るのは陶芸ならではの行為かもしれません。制作の半分は、火の仕事と思っており、自分の思い、願いが強いときはうまく焼ける気がしますね。窯に何日もかけて薪をくべる行為は、思いを積み重ねていくという行為だと思っています。」
「窯に作品を入れるときは、自分の想いを込めますね。最後に作品の完成を火の神様に託します。ここで祈るのは陶芸ならではの行為かもしれません。制作の半分は、火の仕事と思っています。自分の想い、願いが強いときはうまく焼ける気がするんです。窯に何日もかけて薪をくべる行為は、想いを積み重ねていくことだと思っています」
加藤さんのあたらしい作品も販売開始しましたので、あわせてお楽しみください。

B-OWNDは今後も様々な企画をしていきますので、引き続きB-OWNDマガジンやB-OWNDのSNSをぜひチェックしてみてください。
関連記事
- 1 「Stay at Home with ART」企画第1弾 陶芸家・加藤亮太郎氏のぐい吞み新作を販売&オンライン飲み会開催
- 2 「Stay at Home with ART」企画第2弾 陶芸家・古賀崇洋氏のぐい吞み新作を販売&オンライン飲み会開催
- 3 「Stay at Home with ART」企画第3弾 ガラスアーティスト・ノグチミエコ氏のグラス、宇宙シリーズ最新作の土星作品を販売
- 4 「Stay at Home with ART」企画第4弾 漆芸家・若宮隆志オンライン作品説明会を開催
- 5 「Stay at Home with ART」企画第1弾 陶芸家・加藤亮太郎氏とオンライン飲み会を開催しました