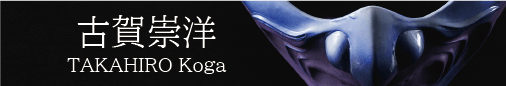コレクターズインタビュー 医療とアート|いのちと向き合う医師がアートに見出した可能性
そう語るのは、脳神経外科医として活躍する道下将太郎氏。
医師として、生と死という「答えのない問い」に挑む心根には、
常に一人ひとりの患者の「いのち」と向き合おうとする誠実さがあります。
コレクターズインタビュー第6弾では、若き医師・道下氏が、
なぜアートをコレクションしているのか、その理由について伺います。
編集:B-OWND
写真提供:道下将太郎
PROFILE
道下将太郎
脳神経外科医 / 環境宇宙航空医学認定医/メディカルスタイリスト。2016年 東京慈恵会医科大学医学部医学科卒業。同大学脳神経外科入局。同年、環境宇宙航空医学認定医取得。2020年、死や障害に対して前向きに豊かな時間を作るサポートをする、株式会社Re・habilitationを創業。同年、新橋、銀座、表参道にトータルコーディネートのクリニックとして、MCC、エメラルドクリニック、Mural clinicを展開。2021年医療法人Medical Wellness Partnersを創業。同年、Art×Medicalをテーマとした株式会社一 一創業。大学時代にはハーバード大学、台湾大学含め、留学歴多数。
医療の先に見据えるもの
―道下さんは、 脳神経外科医としてのご活躍はもちろん、株式会社Re・habilitionにて「治すための」リハビリテーションから「楽しむための」リハビリテーションという理念のもと、一人ひとりが豊かな晩年を過ごすための事業を展開されています。改めて、道下さんが医師を目指した動機や活動の主軸に置かれている問題意識についてお聞かせください。
道下 この世にはいろいろな職業がありますが、小さい頃から「いのち」に関わる医師という職業に大きなやりがいがあると思っていました。私の家系は祖父の代までずっと医者だったので、その生き方を身近に感じていたのかもしれません。そういった経緯のもと医師となり、これまで勤務を続けてきたなかで見えてきたことがあります。

医療技術が発展することに伴い、従来では治療が困難だった病気や怪我は、着実に減りつつあります。けれども、手術が成功して寿命が延びたからといって、その人が幸せな最期を迎えられるとは限りません。むしろ、医療技術によって、本人が望まない過酷な闘病生活を余儀なくされることもあります。医師はあくまでも医療サービスを提供するだけなので、「患者さんが豊かな最期を迎えられたのか?」という死生観の課題まで向き合えている方は少ないのが実情です。
しかし、これまでたくさんの人たちの最期に携わるなかで、「本当にこれを望まれていたのか?」という疑問を感じざるをえませんでした。医師が人の寿命を左右する以上、人生の豊かさを育める機会を医療サービスの基盤に据えて、患者様と深く関わる必要があると思っています。
とはいえ、これに関しては、医療技術だけ、教科書で学んだことだけでは到底太刀打ちできません。そもそも、今の医療には「最期の最期まで、人生を楽しむ」という視点が欠如しています。介護保険が完備されていることから、最低限度の生活を送ることはできますが、そこにはとても大切な、人生を楽しむという考えは全く反映されていません。
要するに、一人ひとりが自分の最期をよりよく迎えるために、好きなことを自由に選択できる環境が整っていないのです。ここに一矢報いることが私のテーマだからこそ、「楽しむための」リハビリテーションを提供するビジネスを展開しています。
もし今、入院している母親が危篤状態になったとして、急いで大部屋に駆けつける。病室内のそれぞれの部屋はカーテンで仕切られているけれども、隣の人のいびきが聞こえるかもしれない。あるいは、そこにいる人たちの病状によっては悪臭がすることもあるでしょう。
また、深夜に臨終を迎えた場合、担当外の医師や看護師が看取りにきて、死亡時刻だけが伝えられて流れる様に病院を後にします。その後は病院が用意した浴衣を着せて、葬儀業者を待つことになります。医者にとっては日々の日常であるため、単なる作業になっていると思います。これがリアルです。
だからこそ、自分の人生を楽しみながら、最期の瞬間は大切な人の手を取り、みんなに囲まれながら「畳の上で死ねる」ような場所を作りたいんです。「施設」や「病院」といった生活空間とかけ離れた場所ではなく、その人が生きる日常のなかで医療を受けられ、カラオケやバーなどエンターテイメントを楽しみ、当たり前のなかで最期を迎えられる場をイメージしています。
答えのないものと向き合う|死とアートの共通点

―核家族化や宗教の不在といった背景から、現代社会を生きる日本人の多くが「死」をどこか遠いものに感じているはずです。「死」を意味付けるための経験や精神的基盤が失われていくなかで、個人が「人生の豊かさ」を追求するには、何がポイントになるのでしょうか?
道下 おそらく、答えのない現実に回答を与えるための軸を持つことが重要なのではないでしょうか。それこそ、アーティストが自らの問題意識を作品として表現して、世に送り出すまでの向き合い方と似ているのかもしれません。死生観に決まりきった答えがないように、アート作品にもまた正解がない。捉え方次第で如何様にも変化するトピックに対して自分なりの「意味付け」を成立させるためには、重心となる価値観を表現する力を養わなければ、死をはじめとする不確実な問題と向き合うことはできないはずです。だからこそ、医療技術が立ち入ることのできない人生の豊かさを考えたり、感じたりする素地を問いかけるものとして、アートの世界観に大きな可能性があると思っています。
私は死期が迫る患者さんには好きなことをしてもらいたいと思っています。そこで、病室を本人の家のような環境にすることがあります。「自分の身の回りに置きたいものを持ってきてもいいですよ」と話したときに、その人が持ってくるものこそが一番のアートだと思っています。
例えば、紙風船でも、人形でも、周りから見れば「何の価値があるんだろう?」と思えるようなものでも、その人にしかわからないこだわりがちゃんとあって、そのものを通して自分の人生を振り返る鏡のような存在になっているものがあります。それは最早、自己を投影したアート作品と言ってもよいのではないでしょうか。
―その「もの」に、その人の物語が詰まっている。それがアートに等しいという感覚はよくわかります。
道下 はい。人生の最期を迎えようとする人たちが残された時間をともに過ごすために選んだものには、その人たちの生き様が反映されているような気がしています。これに関連して、私は現在、友人と一緒に死装束の制作にも携わっています。

写真提供:道下将太郎
人間は赤ん坊として生まれてくるときは何ひとつ自分で選択できません。けれども、死にまつわる事柄は、葬式をはじめ、自分の意思で決められる範囲が広いのです。とりわけ、衣・食・住という生活の三大要素のなかで「衣」は肌と同じように身にまとうもので、現代人にとって自己表現のツールとなっています。それなのに、今、死装束を生前に自ら選ばれる方はとても少ないと思います。
人生の最期を締めくくるのに相応しい、自分でも着たいと思えるような死装束を生きているうちにデザインすることが大切であると思っています。死について考え始めると、喜怒哀楽の感情が噴出して、暗い、恐ろしい衝動にとらわれることもあるかもしれません。それもまた生きる、死ぬということです。また、「死」は残された方々のためにもあります。死装束を通じて、本人がここまで深く死と向き合っていたのであればと、残された側の納得感にも繋がっていくのではないでしょうか。
―死装束の制作を通じて「死」と間接的に向き合う機会を作るということは、非常に面白い取り組みだと思います。改めて、医療現場を通じて死といった抽象的なものと日常的に向き合う道下さんからすれば、アートという媒体がなかったとしても医療現場を通じて自分の軸を常にクリアに保っていけるような気がするのですが、なぜ、アート作品を購入されているのでしょうか?
道下 私にとってアート作品は、そのとき、その場所で絶えず見え方が変わり続ける無限の側面を持っているような存在です。例えば、昨日見ていたときは「いやー買ってよかった」と思っても、今日、改めて見ると「俺、なんでこんなものを買ったんだろう」と疑問に思うこともある。そして、明日はまた見え方が変わっているかもしれない。でも、それでいいというか、それだからいい。瞬間、瞬間のあり方がまったく固定化されることがありません。これは自然にも共通していて、どこを見ても、同じ景色は何ひとつとして存在しません。その自由な有りさまを表現する、アートの営みに惹かれているのだと思います。
人間社会で生きていると、欲にまみれたり、タスクを課されたりして、そのときの鬱々とした自分が延々と続いていくような錯覚に陥る場面ってあるじゃないですか。でも、本当は同じ毎日なんてあり得ない。かと言って、この感覚を取り戻すために、ルーティンワークとして自然に触れる時間もありません。だから、アート作品を手元に置くことが、日常生活のなかで自然を感じる機会になっています。
コレクション紹介 | アートからさまざまなものを感じ取る
―ここからは、道下さんのコレクションをご紹介いただきたいと思います。 こちらの作品を作られたアーティストと、購入された理由についてお聞かせいただけますか。

写真提供:道下将太郎
道下 これは金沢で活動する漆作家・田代瑠緒さんの作品です。この世界には、さまざまな黒が存在しますが、黒中の黒、最も美しい黒は「濡れたカラス」の姿だと思っています。漆の黒には、そこに共通する瑞々しく生きるような「黒」を感じるんです。きっと、その淀みのない水面のような黒に魅了されているのでしょうね。
漆の職人さんたちとの繋がりもあり、ウルシの木から樹液を採取して作品に落とし込むまでのストーリーを伺ったときに、地域の伝統工芸として「純粋に応援したい」という気持ちになったことも購入の背景にあります。
―これは有名な話ですが、スティーブ・ジョブズが初代iPhoneをデザインするときに影響を受けたものとして、東京国立博物館に展示されていた漆をまとった印籠があります。手にとってみたくなるような魅力が漆にあるのは世界共通のことだと言ってもよいかもしれません。

写真:木村雄司
―道下さんはB-OWNDに参画する陶芸家・古賀崇洋さんの新作《NEO MANEKINEKO》シリーズもご購入いただいておりますが、コレクションの決め手は何だったのでしょうか?
道下 一目惚れしてしまったんです。作品から湧き上がる力強い想いのようなものを感じました。
古賀さんの「招き猫」にはいくつかの種類がありますが、そのなかで唯一、顔がはっきりと見えていたのがこの作品でした。医師は、患者さんのことを「目」で見て、その人にとって最も必要かつ的確な言葉を選んで「口」で伝える仕事でもあります。この作品を選んだのは、それが決め手になりました。

写真:木村雄司
―また、陶芸家・奈良祐希さんの作品《Bone Flower》もご購入いただきました。
道下 この作品も即決でした。一見すると、単調な作りのようですが、いろいろな見方ができる、非常に奥深い作品だと思います。まさに「祈り」というコンセプトのとおり、朝日に照らされたような温かみを感じました。
以前、アフリカでマサイ族と交流をしたことがあります。そのとき、大きな象が亡くなった場面に出くわしました。アフリカの大自然ならではの光景ですが、その象を中心に、空には何百ものハゲタカが飛び交い、大地にはライオンがいて、その近くにはハイエナが集まっていました。まるで、小さな食物連鎖を目の当たりにするようで、改めて生きる死ぬということが怖いと感じました。ですが、マサイ族からすればそれは、日常の風景のひとつであり、「その象は次の生命につながっている」という考え方なのです。
その時私は、何となく解せない気持ちでいたのですが、よく見ると、その象の近くで子どもの象も死んでいました。ですが、どの動物も子どもの象にはまったく手をつけませんでした。実は、その象は病気だったんです。すると、マサイ族は「土に還れないから次の生命に繋がらない」と言って、子どもの象の火葬をはじめました。それも、夜通しです。
その宴で、マサイ族の子どもたちは当たり前のように生命の話をしていました。そこではじめて、彼らの言わんとしていたことが腹に落ちた感覚になったんです。そのときに見た朝日、そしてマサイ族の人たちが祈りを込める炎の温かみ、それが奈良さんの作品と重なったのです。独特の表現かもしれませんが、生命を慈しむような温もりが、作品に落とし込まれていると感じました。
「あるがまま」であることを受け入れる

―肉体的にも精神的にもハードな業界に身を置いていらっしゃる道下さんですが、ご自身が掲げる「ブレない」理念のようなものはありますか?
道下 難しい質問ですね(笑) 。敢えて言えば、私は根本的には「すべてはあるがまま」と思っています。これが正直な心根です。以前は、細いところまで計画を立てながら、一つひとつのことを明確に位置付けていました。それこそ、医師はこうあるべきだとか、コミュニケーションはこうすべきだとか、いろいろなことを決めきっていました。
ですが、それが崩れたときに落ち込んだり、想定外の出来事がいくらでも起きたりする現実を目の当たりにしていくなかで、あるがままの自然を受け入れて、それを活かし続けることの重要性を思い知りました。
たとえば、水面に浮かぶ笹舟のようなイメージです。絶えず水面の揺れに影響を受けるなかで、いろんな動きをするけれども、笹舟という存在が向かっている方向はブレない。楽しみながら進むことも大切です。その感覚が自分にあるからこそ、予測不可能な事態がいつ起きても、その時々にあった対応をしようとする姿勢が保たれていくのだと思います。
―あるがままを受け入れる。でも、それは決して「何でもありでどうでもいい」という虚無的なものではないということですね。現実の有り様を絶えず価値あるものに昇華させようとする主体性があるからこそ、道下さんの柔らかくも奥行きのある佇まいがあるのかもしれません。この度は、仕事観やアートに対する価値観に触れて、心から感動いたしました。貴重なお話を聞かせていただきまして、本当にありがとうございました。
関連記事